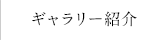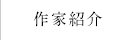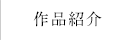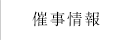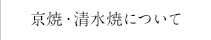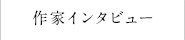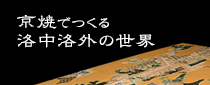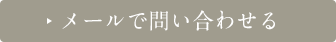作家インタビュー
鎌田幸二Kamada Koji

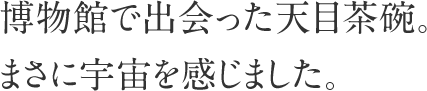


夜空にも海にも似た、まるで吸い込まれてしまいそうな深い色合いと煌めきを放つ天目。身が引き締まるような静かな佇まいと同時に、どこか温かみも感じさせ、見る人を惹きつけてやまない。鎌田幸二さんの天目はそんな、他とは異なる不思議な魅力を放っている。
独特の深い色合いと幾重にも重なるさまざまな結晶や模様を生み出す天目は、喫茶とともに中国から日本へ伝わり、古くから多くの人を魅了してきた。鎌田さんはそれに長年一貫して取り組んでいる、日本の天目の第一人者ともいえる作家だ。
鎌田さんは京都生まれの京都育ち。実家はごく普通の会社員の家庭だったが、幼い頃から絵を描くことが好きだったこともあり、美術や工芸の分野には早くから興味を持っていたそうだ。
大きな転機となったのは高校卒業後。鎌田さんは、友人の紹介で、五条通の近くにあった共同の登り窯に手伝いに入ることになった。それが、鎌田さんのやきものとの出会いだった。
「そこでは清水正さんという方が共同の登り窯に行っておられて、数年間お手伝いをしていました。そのうち、自分でも窯を使わせてもらったり、ろくろの技を学びました。それでやきものも面白い、やってみようかと思うようになりました」
鎌田さんはその後、京都府立陶工訓練校に入学。卒業後も訓練校内の成形や窯などを担当する指導員として勤務しながら創作活動を続けた。
鎌田さんが天目に本格的に取り組むようになったのも、ちょうどその頃のこと。一番のきっかけは、勉強も兼ねてしばしば出入りしていた京都国立博物館で目にした一つの茶碗だった。
「前から天目というもの自体は見たことがあったのですが、特に印象深いのは訓練校時代に博物館で見た南宋時代の禾目天目。これがとても見事で。まさに宇宙を感じましたね」
天目は、その独特の色合いや結晶の煌きを、しばしば星や宇宙に例えられる。鎌田さんも天目のそんな神秘的な魅力に強く惹かれ、自らもやってみたい、と強く思ったそうだ。
天目を手がけるにあたり、鎌田さんは、まず古典の名品を学び、再現することから研究を始めた。そして、最初に取り組んだという油滴をはじめ、さまざまな作品に繰り返し挑戦した。どのようにすれば古典作品のように美しい天目を生み出せるのか、試行錯誤の日々が続いた。
「同じ調合の釉薬でも、窯に入れる位置によって仕上がりは大きく変わります。特に登り窯の場合、各部屋で温度はもちろん、火のまわり方なども違いますし、生焼けになることもあります。それをもう一度焼きなおしてみるとまた表情が変わる。登り窯で焼くことがそのまま実験になっていて、とても勉強になりました」
その後、条例規制などの影響で五条坂周辺の登り窯が廃止されることになったため、鎌田さんは1980年に自宅にガス窯を築窯し、以降はガス窯での作陶が主体となり、ガス窯の特性を活かした天目研究は数十年変わることなく続いた。
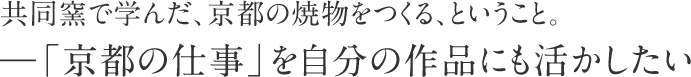

天目の研究を続けるうち、鎌田さんは古典の再現だけでなく、自分なりの天目の表現を求めるようになっていった。その上で大きな糧となったのは、共同窯で得た経験だったという。
鎌田さんは訓練校と並行し、五条坂の共同窯にも続けて出入りし、制作を行っていた。
「僕が通っていた当時は、近所の色々な作家さん達と共同で窯を詰め、焼いていました。それらの仕事を通じて色々な作品を見られて大変勉強になりましたし、刺激を受けましたね」
同時代に活躍しているさまざまな作家との交流を通し、鎌田さんが特に学んだもの。それは、京都でやきものを作ること、「京都の仕事」に対する意識だったそうだ。
「昔から京都の作り手は、轆轤がいい、品がよい仕事をするといわれます。自分も京都でやきものをやるからには、そんな「京都の仕事」を自分の作品にも活かしたいと思ったんです」
長く日本の都として繁栄してきた京都には、優れた審美眼や美意識をもつ公家や武家、商人といった注文主が多く、同時に彼らの声に応える職人たちも昔から多く暮らしていた。都に相応しい、より品の良い品を作り手は求められ、数多くの品を生み出した。そしてその歴史と経験は世代を越えて受け継がれ、「京都の仕事」という個性となっていった。
鎌田さんはそれをさまざまな作り手と作品に触れるなかで感じ取り、やがてそれが自分なりの天目を生み出す上での大きな支柱となっていったのだろう。
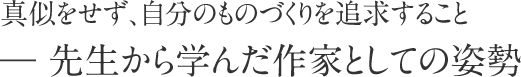

そしてもうひとつ、鎌田さんにとって忘れてはならないのは、人間国宝の清水卯一さんの存在だ。
卯一さんも鎌田さんと同様、中国陶器に学び、天目をはじめ鉄釉を駆使した作品で高く評価を受けた作家だ。鎌田さんは卯一さんのご子息・保孝さんと訓練校時代からの友人で、その縁もあり、卯一さんから指導を受ける機会に恵まれたそうだ。
鎌田さんが卯一さんから学んだこと、それはやきものを作る上での姿勢そのものだった。
「先生はもちろん、先人の作品を真似しないこと、自分のものづくりを追求すること。卯一先生からはそんな心構えや姿勢を学んだように思います。昔のものや他人がやっていたことを、良いからといってそのまま自分もやるだけではいけない。自分の表現したいこと、自らの個性を生かすことが大切だ、ということですね」
その後、鎌田さんはその姿勢を胸に今日までやきもの作りを続けている。


天目は他のやきものに比べて非常に“不安定”である、といわれる。仕上がりをある程度予測することはできるが、どんなに計算しても自分の思い通りにはならない。特に、天目特有の結晶のような輝きは、釉薬に含まれる鉄分などが焼成時の環境によって大きく変化することで生まれるため、コントロールが非常に難しい。鎌田さんいわく、数多く作ってもそのうち納得のいくものは数個できればいい、という程度だという。それほどまでに天目は難しく、手間と忍耐を要するものなのだ。
しかし、鎌田さんはそこに天目の面白さを感じているという。
「絵付けは自分の手で直接描くものですから、ある程度自分の思いに近い模様を出すことができます。でも、天目は釉薬の成分や火加減に頼る部分が多いので、なかなか自分の思い通りにはなりません。そんな人の手の及ばなさが、かえって魅力に感じるんです」
思い通りにいかないからこそ、失敗もすれば、逆に自分の予想以上に素晴らしいものができることもある。そんな一品ができた時は本当に嬉しい、と鎌田さんは笑う。
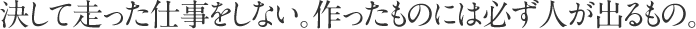
かといって、決して妥協することはない。釉薬の色、素材の土、器の形にいたるまで、全体の調和がとれているか。鎌田さんはそれを常に意識しているそうだ。
「使う釉薬によって、それに合う土も違いますし、形も変わってきます。ろくろの回転ひとつとっても、速くするか遅くするか、一定にするか否かだけでも、器の形は変化して表情も異なってきますから」
土は釉薬の色味や透明感、結晶の出方などにあわせ毎回ブレンドし、サイズや形も釉薬の色や景色をもっとも活かせるものを考えて決めているという。鎌田さんはどの作品に対しても、それほどまでに心を配っているのだ。
「大きなものでも小さなものでも、決して焦って作らない。走った仕事をしないように、いつも心がけています。作品には、必ず作った人の人間性が出るものですから」
作ったものには人が出る。鎌田さんのこの言葉の意味は、そのまま彼の作品が証明してくれている。凛とした風格や品の良さと同時に感じる、深みのある温かさ。それは意図して生まれるものでも、技術のように磨けるというものでもない。鎌田さんの天目は、まさに鎌田さんという人そのものを形にしているのだ。
鎌田幸二

- 1948年
- 京都に生まれる
- 1966年
- 京都府立桃山高等学校卒業
- 1967年
- 作陶を志し、清水正氏の指導を受ける
- 1971年
- 京都府立陶工訓練校専攻科終了
同校指導員(京都府技師)となる
五条坂共同登窯「鐘鋳窯」にて天目の研究を始める - 1972年
- 第二回日本工芸会近畿支部展初入選
第二十回日本伝統工芸展初入選 - 1976年
- 日本工芸会正会員に推薦される
- 1977年
- 京都府立陶工訓練校指導員を辞し作陶に専念
- 1978年
- セントラル・ギャラリー(大阪)にて初個展
- 1979年
- 五条坂共同登窯休止の為、自宅にガス窯を築窯
- 1987年
- 第十六回日本工芸会近畿支部展にて京都府教育委員会委員長賞受賞
- 1988年
- 重要無形文化財「鉄釉陶器」伝承者養成研修会にて清水卯一氏の薫陶を受ける
- 1994年
- 高島屋(京都店)にて「作陶二十五年記念展」
- 1997年
- ニューヨークにて「天目・青磁二人展」
- 1998年
- 東京日本橋高島屋にて「作陶三十年記念展」
- 2002年
- パリにて「陶・漆二人展」
- 2006年
- 第三十五回日本伝統工芸展近畿展にて鑑審査委員(2003年より毎年)
- 2007年
- 第三十五回日本工芸会陶芸部会新作陶芸展審査委員
- 2008年
- 高島屋(大阪店・ジェイアール名古屋高島屋)にて「作陶四十年記念展」
代表作
-

黒地翠青文大鉢
-

燿変油滴茶碗
-

窯変翠青天目茶碗