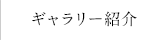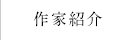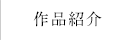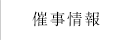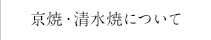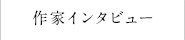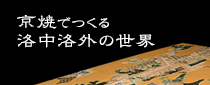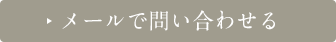作家インタビュー
木村宜正Kimura Noritada




粉引、唐津、天目、青瓷、織部…色も形も様々な作品たち。
ここまで一人で多彩な技法を手がけている作家も、あまりいないのではないだろうか。そう思えるほど、木村宜正(きむら・のりただ)さんの作品は驚くほどバラエティに富み、同時にとても洗練されている。
宜正さんは現在、故郷でもある京都・岩倉の木野を拠点に創作活動を行っている。父・盛伸さんも陶芸家、兄の展之さんも陶芸家という陶芸一家の生まれだ。
「田舎でしたし、それに昔のことですから、周囲にはこれといって遊ぶところもありませんでした。小さい頃からもっぱら父の仕事場を遊び場にしていましたね」と宜正さんは言う。
工房は自宅と通じており、当時はほぼ出入り自由の状態だった。そのため、宜正さんは幼い頃からものづくりをする父の姿を常に見て育ったという。また、粘土を遊び道具に与えられることもあり、何か形を作っては一緒に窯で焼かせてもらったこともあったそうだ。
実際に、小学生の頃に作ったという鬼の面やオブジェが、今も宜正さんのご自宅には大切に保管されている。

「父の姿を見ているうちに、自然と自分も同じ道を選んでいました」
その後、宜正さんは高校卒業を機に京都府立陶工高等技術専門学校へ入学。1年間ろくろの成形技術を学び、卒業後はすぐに父の下で修行に入った。
成形を学んだ後は京都市立工業試験場に進み釉薬の知識を学ぶ、という人も多い。しかし、宜正さんはあえてそうせずに現場に入る道を選んだ。それにはこんな理由があったそうだ。
「とにかく早く現場で何かものを作りたい、という一心でした。できるなら、ずっと一日中ろくろを回して何か形を作っていたい。当時はそのくらいの気持ちでしたね」

師匠としての父・盛伸さんは、あまりあれこれとものを教える人ではなかったという。陶芸家の師匠は、弟子に対しては黙して語らず、という人が多いように思う。宜正さんも、父がものづくりをする姿をただ見ているしかなく、あとはひたすら下仕事の毎日だったという。
しかし工房には、父に教えを請うべく出入りしていた数多くの若手陶芸家たちがいた。修行中の宜正さんにとっての実技指導者は、そんな兄弟子たちだった。
「竹村(繁男)さんは、僕がまだ5歳とかの頃から来ていらっしゃったように思います。小さい頃からよく相手をしてもらっていましたし、本格的な土のこね方や「菊練り」の仕方なども先輩たちから教えてもらっていました」
父や若手の陶芸家たち。そして彼らの生み出す優れた作品たちに囲まれる環境。様々な表現技法を試みながらも宜正さんの作品がどれも高いレベルに至っているのは、この環境が大いに影響したのかもしれない。


宜正さんの作品の釉薬はとにかく多彩で幅広い。なかでも、天目については数多くの色目や模様の作品を生みだしている。
「釉薬の学校に進んでいれば、もう少し効率のいい方法とか本格的な技術を学べたんでしょうけど…調合についてはほぼ独学です。いつも試行錯誤なので、普通の人よりも時間がかかっているかもしれませんね」
通常、釉薬の色調整は小さな破片などに釉薬を塗って作った色見本を用いて行うことが多い。しかし、宜正さんは、実際の作品づくりの中で新たな色のバリエーションを生み出しているという。天目の場合、基本となる釉薬に様々な原料を幾層にも重ねて施釉、焼成する事で複雑な表情が生まれる。ものの形状によっても釉薬の流れ方などが異なる為、出来るだけ日々の仕事の中でアイデアやイメージを少しずつ具現化するよう心掛けているそうだ。

「天目は、やろうと思えばいくらでもバリエーションは増やせるんです。その中で、自分の好きな色のトーンや模様の範囲になるように気を配っています。普通、だけどちょっと違う、というくらいが好きですね」
ぱっと見た時にきれいに見える色、そして突出した派手さや個性ではなく、落ち着いた美しさがある色。それが、宜正さんが考える理想の釉薬の色だそうだ。
しかし、それだけでは良い作品にはならない、と宜正さんは言う。
「どんなにいい色でも、作品自体の形が悪ければ魅力は半減してしまいます。形から学び始めたからなのかもしれませんが、やはり一番気になるのは成形なんです」

器作りは、土を成形した後に一度乾燥させる。その時点で全体の水分が減った分収縮するので、特に膨らんだ形の部分は最初の段階より横に広がろうとする。素焼きをすれば更に収縮する。そして、その上から釉薬をかけると、場所によって薬ののり具合が異なるため厚みも変化し、重ねれば重さも変わる。すると、最終的には作った当初の形とは違ってしまう場合も大いにあるのだ。
「作りたての、まだ乾かしてもいない状態が理想に一番近い形なんです。そこから作業の段階を踏むごとに、形が段々と悪くなっていくように感じていたことが昔はありました」
元々「形を作りたい」一心ですぐに修行に入った宜正さんにとって、ここは大いに気がかりとなる部分だった。もちろん、技術を磨き経験を積むにつれ、後でどのように形が変化するか考慮しての作品作りができるようにはなってきた。
「最初の「一番良い形」を如何に仕上げまで残していくかは、常に意識していることのひとつですね」


また、宜正さんにとって今は、新しいものを身につけると同時に、自分のものづくりを見直す時期にもきているという。
「最初の頃と今では、やっているうちに自分の感覚が変わってきていて。昔はこれがいい、と思っても、今になって改めてできあがったものを見ていると、何か違うと感じることがあるんです。最初は没にしたものも、今見るとあれの方がよかったな、と思ったりもします」
焼き物作りにおいては、ずっと同じ素材を使い続けられるとは限らない。同じ方法で制作しても、以前と全く同じ作品ができるわけではない。だが、長年仕事を続けていると、つい流れ作業のような感覚になってしまい、雑な作陶になってしまいがちだ。だからこそ、一度立ち止まって自分の作品を見つめ直す必要がある、と宜正さんは言う。
「グレードを高める、ともいいますね。確かに経験は重ねてきましたが、本当に良いものを作れているのか?もっと上手くできるのではないか?と、いつも考えています。大きさを変えたり、色目や形を調整したり…ひとつひとつの作品を見直すことによって、より深く豊かなものにしていきたいです」
現状に満足せず、常により良いものを作りたいと求める真摯な姿勢は、宜正さんの強い向上心の現れともいえる。そしてその思いこそが、次々と新しい表現に挑戦し、表現の幅やバリエーションを増やしてきた一番の原動力なのだろう。
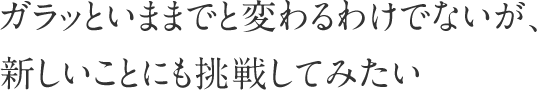

そんな宜正さんに、今後新たに挑戦してみたいことについてお伺いした。
そこで挙げられたのは、「薪窯の作品」。以前、薪窯を持っている人から場所を借りて挑戦してみたことがあったそうで、その時に宜正さんが制作したのは、四角く角ばった形が特徴の、大きな花器だった。
信楽の土は粒が粗く、精製されていないため内部に石や不純物が多く残っている。そのため、精製された土と違い表面は滑らかにはならず、ぶつぶつとした土の粒が浮き出て見える。普段宜正さんが制作されている、上品な風合いの器とは全く違う、武骨で力強い雰囲気の作品だ。
「青瓷や天目のときと違って、薪窯は窯に一度入れたらどんなものができるかわからない。出してみないと予想がつかない。そういうところが面白いな、と思っています」
信楽の土は高温にも強く形が変化しにくいのも特徴だ。また、釉薬を用いないので、土の中に含まれる成分が表面に溶け出して模様を生み出したり、火の当たり方でも色味や風合いも変化したりする。土の雰囲気や作った形が、そのまま作品の表情として表れてくるのだ。この点も、宜正さんにとって今までに無い魅力に感じるという。
「形の作り方とか、ガラッと自分の方向性が変わるわけではありませんが、新しい、今までやったことのないことにも挑戦してみたいですね」
また、器以外の作品も作ってみたい、とも思っておられるそうだ。
「あとやってみたいものといえば、沖縄のシーサー(獅子)。知り合いが作っていたんですが、それがとてもよかったので…自分でもできたらいいな、と(笑)」
今後の挑戦について語る宜正さんの表情は、まるで新しい発見に胸を躍らせている、好奇心いっぱいの少年のように見えた。新しい試みをやってみたい、そしてより良いものを作りたい。宜正さんのものづくりへの興味の広がりは、尽きることがない。
今後の宜正さんの生み出す作品が、どのように広がっていくのか。どのような新しいものが生み出されていくのか。今後の展開に大いに期待したい。
木村宜正

- 1968年
- 京都・岩倉に生まれる
- 1989年
- 京都府立陶工高等技術専門学校終了
- 1992年
- 日本伝統工芸展近畿展入選(以降毎年入選)
- 1995年
- BONSAIの器展入選
現代茶陶展入選 - 1997年
- 日清食品現代陶芸「めん鉢」大賞展入選
- 1998年
- 清水卯一氏主幹「蓬莱会展」出品(以降2004年まで毎年出品)
札幌芸術の森「ビアマグランカイ‘98」入選 - 2003年
- 日本伝統工芸展初入選
- 2007年
- 京都市芸術文化協会主催「CRIA展」推薦出品
日本伝統工芸展入選 - 2008年
- KYOTO&LITTLE KYOTO展出品
ANTHONY d‘OFFAY GALLERY(ロンドン) - 2012年
- 京都美術・工芸ビエンナーレ2012入選
- 各地で個展、グループ展
代表作
-

黒燿天目酒盃
-

朝鮮唐津徳利
-

油滴天目酒盃