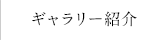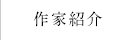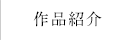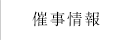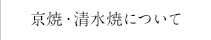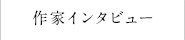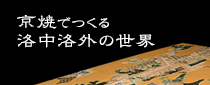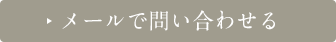作家インタビュー
竹村繁男Takemura Shigeo



工房にて作品の技法について説明いただきました。
淡い緑に濃い緑、黄色、薄紅…様々な色彩に彩られた器たち。
これは皆、自然の灰と炎の力が生み出した色である。
杉、葡萄、ひまわり…様々な素材は、それぞれ違った独特の色を持っている。
京都・山科にて創作活動を行っている陶芸作家、竹村繁男さんは、30年以上にわたって、自然の灰を使って自ら作った釉薬で作品作りを行ってきた、自然灰釉の第一人者のひとりだ。
竹村さんが陶芸家を志したのは高校生のとき。
当時からものづくりの仕事をしたい、と考えていた竹村さんは京都市立日吉ヶ丘高校陶芸科に進み、卒業後は18歳で木村盛伸さんに弟子入り。その後8年間学んだ後に独立し、現在の場所にて自らの作品作りを始めた。
自然の素材を燃やして灰を得、それを用いて釉薬を作ることは、師匠も行っていた手法なのだそうだ。竹村さんが手伝いの過程でその手法を受け継ぐのはごくごく普通のことだったという。
「自然とやるようになりましたね。山から土を取ってきて粘土にするのとあわせて、灰を作って篩(ふるい)にかけて…という作業はほぼ日課になっていました」

竹村さんの灰釉は、素材となる植物や木の枝などを野外で焼き、取り出した灰を用いる。
古くは古代中国にさかのぼる、昔から伝えられてきた手法だ。
技法自体は自然の灰で色を出すだけなのでとてもシンプルだが、素材によってそれぞれ違った色が生み出されるため、とても奥の深い方法でもある。
灰は一度にはたくさんは取ることはできない。トラック何台分もの植物や木の枝を集めても、そこから取れるのはたった一握り。これを水に溶かして、何度も水を取り替えてアクや不純物を取り除き…長い時間をかけてやっと灰釉が出来上がる。
「灰釉を作るには、どんな材料であっても、それだけの単体だけで灰にしないといけないんです。そして、なるべく砂利や土など余計なものが混ざっていないものでなければなりません。そういうものを探すのはとても大変です」
様々な人との出会いの中で材料を見つけることも多いそうだ。
例えば、以前いちじくや葡萄の枝を用いたときは、剪定で出ると聞き、近所や知り合いの農家から譲り受けにいったという。人が必要ない、というものを紹介してもらってそこまでとりに行くことも多いのだそうだ。トラックを借りて大量の素材を取りに向かったところ、とても積みきれないのでその場で焼いてから持ち帰ったこともあったという。
素材を探し回り、伝を頼って問い合わせ、やっとのことで手に入れて持ち帰っても、釉薬に仕上げてみると同じ素材のはずなのに色が違っていた…ということもあったそうだ。

御子息で陶芸家の陽太郎さんと、窯での1枚。
「素材が採れた土地や、枝や幹など使う箇所によっても、特性や色が変わってしまうんです。自然の灰は、いざ焼いてみないと何が出てくるかわからない。ここが面白いんです。その個性をどういう組み合わせで引き出して、使っていくかを考える。そこがポイントだと思います。」
自然の灰は特性もそれぞれ異なってくる。色々な手を加えなければ使えないものもあれば、ほとんど何もしなくてもよいものもあるのだそうだ。
例えば、普通は灰を釉薬にする際、長石や石灰石など他の成分を加えなければなかなか水に溶かすことができないのだが、八朔(はっさく※ミカンの仲間)の灰の場合は、水にあっさりと溶けてしまうのだという。
最初は白い灰。それを丁寧に釉薬に仕上げ、そこから釉薬に合った配合や温度、焼き方、表現を模索していく。釉薬の個性を見出し、その特徴を生かす作業。試行錯誤を繰り返して、理想の作品が生み出されていく。

扱う灰によって、野外の穴窯と細かな温度管理ができる電気窯を使い分けているという。
例えば、竹村さんの代表作ともいえる「ひまわり」の灰を使った作品。
やわらかく美しい黄色はまさにひまわりの花の色だが、これを生み出すには大変神経を使うという。
「ひまわりは気難しい。安定性が悪いので、ほんの一度温度が違っただけで、釉薬は溶けなくなるし、この色が出てこない。ある一定の温度になると、それまで全く溶けなかった釉薬が急に溶けてくるんですよ。うまく扱えるようになるまでには3年はかかりましたね」
扱う灰のなかでも特に繊細なひまわりは、焼き上げる際にも微妙な温度調節が必要になる。そのため、野外の穴窯では絶対に焼くことができない。
一度二度違うか否かの際どさが問われるので、細かな温度管理ができる電気窯で慎重に仕上げなければならないのだそうだ。
「そういう薬を入れて安定させることもできます。でもそうしてしまうと、灰の持っている本来の個性を殺してしまうことになる。不安定さもひとつの個性で、面白さなんだと思っています」
楽な方法をとることは簡単だが、それでは個性も何もなくなってしまう。
良いところもそうでないところもひっくるめてその灰の特徴として受け入れ、それをどう生かしていくかを、竹村さんは大切にしている。
まるで、個性豊かな子供を育て上げていくかのようだ。
「灰は一度にほんの少ししか取れませんからね。その分、可愛さが増すんです」
そして同じ釉薬でも温度や環境の違いで、自在に表情を変える。たとえば同じ葡萄の灰を使った作品でも、ほんのり緑がかったものもあれば、特に顔料を入れなくても、少し調合を変えれば淡いワイン色に発色が変化する。
「灰を振るう篩の目の粗さでも違いが出てくるし、土地や使う土、焼く窯によっても色がかわってきます。これしかない!という表現を見つけるために、とにかく何度も試して、時間をかけます」


杉灰のかかった長平皿。伸ばしたり、引きちぎったり…形の表現がその色みを際立たせています。

作陶に対する思いなどさまざまなお話をお伺いしました。
釉薬の個性をもっともよく生かすためには、形の表現も大切な要素だ。
杉灰のかかった長平皿は、板状に伸ばした土を板や床にたたきつけて引き伸ばし、両端は手で引きちぎって成形したそう。確かによく見ると指の跡も残っており、エネルギッシュでどこか荒さを感じさせる形になっている。
また、杉灰は焼き上げると濃い緑色を発し、透明感あるガラス質の溶け方をするのだが、引き伸ばされたことで釉薬溜りの部分に細かなひび割れが生じ、輝きが増している。
ところが、これと同じ表現はひまわりの灰釉を用いてはできない。
対照的に、ひまわりを使った作品はどれも肌が滑らかで、つるりとやわらかな、繊細な形をしたものが多い。その上に、全体を包み込むようにふんわりと、黄色が包み込んでいる。流れが綺麗な釉薬であるため、できるだけ流れを妨げることがないよう、凸凹を出来るだけ排除した形を心がけているのだそうだ。
その釉薬の個性を生かすためにぴったりの形と表現。まさに一期一会の表現との出会いだ。
しかしそれは決して「偶然」ではないのだ、と竹村さんは言う。
「素材との出会いはたまたまかもしれませんが、表現に”偶然”ということはありません。それを自分の中で戒めとしています」
「たまたまこうなった」ではなくて、「こうしたからこうなった」。
例え自分の予想を超えていたとしても、生まれた結果には必ず理由がある。そこを追求せずに偶然、で終わらせることはしない。
「ひとつひとつの作品に出る色は、常にここをどうするか、どうしたらよいかとアンテナを張っていて生まれるもの。つきつめて出す”必然”なんです」

昨今では、灰作りの段階から自分で釉薬を作る人は少ないという。簡単に理想の色を出せる配合を済ませた釉薬も出回っている。
自然の灰からひとつの作品を理想の形と色で生み出すためには、途方もない時間と苦労が伴うものだ。
しかし竹村さんは「普通の仕事です」と仰る。その口ぶりは、決してそれを苦と感じるものではない。
「むしろ灰を作っていくその過程で、少しずつどんなものを作ろうかと考えている気がします。灰を作るその段階で、もう作品作りは始まっているんじゃないかと思いますね」
数ある作品のうち、特に竹村さんが作るのが好きだというのが、土瓶だそう。
湯呑や皿と異なり、土瓶や急須は注ぎ口や茶漉しの部分、蓋といくつもパーツが分かれており、工程も複雑で、制作に大変手間がかかる。そのため、公募や展示で出されることも少ないのだそうだ。
だが、竹村さんはその手間こそが楽しいと仰った。

作陶に対する思いなどさまざまなお話をお伺いしました。
「いくつものパーツに分かれているものを、ひとつひとつ組み立てて出来上がる。それが面白いんです」
内部の漉し器部分も自らの手で穴を開け、注ぎ口も使いやすいように丁寧に調整。
持ち手の部分も、籐を自分で巻きつけて取り付けている。
ひとつひとつの細かな箇所に、竹村さんのこだわりと思いが詰まっている。
「でも、これだけ手間かけても、どんなに面白いといわれても格好いい見た目でも、こういうものは結局使えなきゃ仕舞い!なんですよね。でも制約があるということは悪いことではない。その中でどう真剣に遊べるかが面白いんだと思います」
手間を惜しまないその真摯な姿勢は、竹村さんの作陶に対する思いそのものだ。
「基本の段階で手を抜いたり、ちょっとずるをしたりすると、必ず最後にしっぺ返しがきます。丁寧に仕事をすると、結果が伴ってきます。ものづくりというのは、きちんとやると応えてくれるものなんです。最後の一手は、それまでやってきたことの力がはっきりと結果になってくるんですよ」
特段、特別なことではない。でも、当たり前のことがもっとも大事なのだ。ものづくりにまっすぐに、真剣に向き合ってきた人らしい言葉だ。

今日もまた窯から新たな作品が生まれています。
「焼き物というのは、必ず最後に焼くという行為に至ります。ある程度の温度管理はできますが、作品を窯に”委ねる”ことになる。そこで、それまでやってきたことの結果が全部出てくるんです。だからこそ、如何にそれまでの過程に自分の思いを入れ込んでいくか、が大事なんです」
竹村さんはこれからも、使ったことのない素材に出会う機会があるなら、ぜひ新たな灰釉に挑戦したいと仰った。
「何か新しい素材が出ると何とかして使いたい!生かしたい!と思ってしまうのが性分なんですよね(笑)本当に無限の可能性があると思います。この先もいろいろなものに出会って、そこからまた、その灰だけが持っているものを引き出した作品を作っていきたいですね」
灰との出会いは運だ、という竹村さん。どこですばらしい素材に出会えるかは予想できない。だからこそ、この先が楽しみで、面白いのだという。
まだ見ぬ出会いと、それを育てていく手間と過程そのものを楽しむ姿勢が、竹村さんの作品を生み出し、支えている。
竹村さんがこの先、どのような素材と「出会い」、どのように灰と土に隠れた個性を引き出し、私たちに新たな色、作品との「出会い」を導いてくれるのだろうか。楽しみでならない。
竹村繁男

- 1953年
- 京都山科に生まれる
- 1972年
- 京都市立日吉丘高校陶芸科卒業
木村盛伸先生に師事する - 1975年
- 第四回日本工芸会近畿支部展初入選以来毎年入選
- 1978年
- 京都府工芸美術展入選
- 1980年
- 独立し山科に大日窯を開窯する
- 1988年
- 第三五回日本伝統工芸展入選
- 1989年
- 「土の子会」結成
- 1990年
- 第三七回日本伝統工芸展入選
- 1994年
- 「蓬莱会作陶展」に出品
- 1996年
- 第二五回日本伝統工芸近畿展 奨励賞受賞
大阪難波「高島屋」にて個展 - 1998年
- 第53回新匠工芸会展入選
- 2001年
- 京都工芸美術作家協会展
- 2002年
- 第49回日本伝統工芸展入選
- 2003年
- 岡山高島屋画廊にて個展(以後隔年で3回)
- 2005年
- 横浜高島屋美術画廊にて個展 (08年)
- 2006年
- 京都高島屋美術画廊にて個展(10年)
- 2007年
- 第36回日本伝統工芸近畿展京都府教育委員会 教育長賞受賞
第54回日本伝統工芸展入選
日本工芸会正会員に認定される - 2008年
- 日本工芸会陶芸部会正会員による第36回新作陶芸展 日本工芸会賞受賞
第五五回日本伝統工芸展入選 - 2009年
- 第五六回日本伝統工芸展入選
- 2010年
- 「第39回日本伝統工芸近畿展」にて鑑査委員に就任
第57回日本伝統工芸展入選
代表作
-

陽向釉 花生
-

陽向釉 土瓶
-

灰釉 ぐい呑